優れた技術力で事業を飛躍させたり、勤務体系や福利厚生、そして働き方改革への対応などで独自性を発揮して注目を集めている企業をインタビューする本企画。
今回はクレジットカードの不正対策ソリューション「ASUKA」を展開する株式会社アクルに、不正利用の実態や事業の特徴などを伺いました。そして独自の働き方改革としてスタートした「水曜日午後の休暇制度」や、近い将来の導入を視野に入れている週休三日制、さらにはフルフレックス&フルリモートの勤務体系をお聞きするとともに、採用におけるポイントを伺いました。
株式会社アクルとは

▲株式会社アクルのミッション(公式ページより引用)
2016年7月に設立された株式会社アクルは、ミッションに「『決済』にかかわるあらゆる課題を解決していく」(決済を自由に、もっと楽しく、より安全に)を掲げています。メイン事業はクレジットカード不正対策ソリューション「ASUKA」の提供と、チャージバック保証サービスの二つです。
また、労働環境の拡充にも注力しており、フルリモート&フルフレックスタイムの導入や、時短勤務・副業の承認、さらには書籍購入制度や資格取得補助制度などを採用しています。2023年2月からは独自の働き方改革として「水曜日午後の休暇制度」をスタートしています。
| 会社名 | 株式会社アクル |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14階 |
| 事業内容 | クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証サービス、集客支援サービス他 |
| 設立 | 2016年7月 |
| 公式ページ | https://akuru-inc.com/ |
| 働き方 | フルフレックス、フルリモート |
今回は、事業の特徴や働き方、独自の休暇制度の導入経緯や当面の狙い、そして近い将来の導入を見据えている週休三日制についてお聞きしました。フルフレックス&フルリモートの勤務体系や、独自の社風「大人ベンチャー」、採用におけるポイントも伺います。
クレジットカード不正利用の被害からお店を守る

編集部
最初にアクルさんの事業概要について、ご説明をお願いします。
渡辺さん
アクルはクレジットカードの不正対策ソリューション事業を手掛けています。不正対策に特化した、ニッチな珍しい会社です。
「クレジットカードを誰かに勝手に使われた」という話を、お聞きになったことがあると思います。クレジットカードの情報が漏れ、カード番号や有効期限、裏面に書いてあるセキュリティコードなどを知った第三者が悪用したということです。
カード情報の取得方法は、悪意のある人が直接盗む場合もありますが、ほとんどは闇サイト(ダークウェブ)での購入になります。ハッカーのような人々が、大量の盗まれたカード情報を闇サイトで販売しています。
これらの闇市場に流れ込んでしまったカード情報は、悪意のある人々によって簡単に悪用されてしまいます。クレジットカードは仕組み上、カード番号と有効期限さえわかれば、誰の手に渡ったとしても不正利用されてしまう可能性があります。
編集部
カード情報さえあれば、誰にでも簡単に使えるんですね。
渡辺さん
そうです。そして不正利用された場合でも、カードホルダー(カードの持ち主)にはカード会社からの請求が届きます。しかし「私はこれを買っていない」と申告し、カード会社がそれを認めれば、カードホルダーへの請求は取り消されます。
編集部
カード会社や保険会社が補償してくれるんですね。
渡辺さん
そう思っている方が非常に多いのですが、実は違います。カード会社は本来、カードホルダーから回収した利用代金の中から、カードが使われたお店に支払いをします。ところが不正利用の場合、カードホルダーはカード会社に対して利用代金の支払いを拒否することができます。この場合、カード会社はその利用代金を取り消すことができます。このプロセスは、業界では「チャージバック」と呼ばれています。
チャージバックが発生すると、カード会社は利用代金を回収できないので、お店には支払いをしません。つまり誰が一番困るのかというと、カードを不正利用されたお店となります。商品の代金を支払ってもらえませんし、商品が戻ってくることもないので、その損害は多大になります。
チャージバックはカードホルダーを不正利用の損害から守るための仕組みなのですが、そのリスクはお店が負う形になっています。
編集部
カード会社とお店とは、そういう契約になっているのですか。カードホルダーの多くは、そのことを知らないでしょうね。
渡辺さん
そう思います。ですからお店からすると、不正利用によるチャージバックの被害をどうやって減らすのかが、非常に重要となります。そこでアクルでは、こういった不正を減らすためのソリューションとして、不正検知サービス「ASUKA」を提供しています。そして日々、お店の方と一緒になって、不正利用者たちと戦っています。
編集部
クレジットカードの不正利用による被害額は、どれぐらいあるのですか。
渡辺さん
2022年は約420億円まで拡大しました。1日1億円以上の被害が出ている計算です。国としても問題視し始めており、対策に本腰を入れつつある状況です。
チャージバックを減らすソリューション「ASUKA」
編集部
アクルさんが提供しているサービスについて、もう少し具体的にご説明いただけますか。
渡辺さん
大きく分けますと、一つは不正利用による「チャージバックを減らすサービス」です。これが先ほどお話したソリューションの「ASUKA」です。そして、もう一つは、チャージバックが発生してしまった場合に、その被害額を「保証するサービス」です。
編集部
まずASUKAの特徴からお願いします。
渡辺さん
クレジットカードの不審な取引を自動でチェックし、決済を完了する前に注文をブロックすることができます。
例えば家電など不正利用者に狙われやすい商材を扱っているお店の方は、クレジットカード決済による高額商品の注文が入った場合には、細心の注意を払います。何をするかといいますと、まずは注文情報の確認です。名前、住所、電話番号、メールアドレスなどについて、おかしな点がないかを目視にてチェックします。
そのうえで不審な取引があった場合には、本人利用であるかどうかを確認するためにメールや電話で連絡を取る必要があります。この作業は非常にストレスが溜まるものです。
しかしASUKAを使うと、注文情報の名前や住所、電話番号以外にも、目では見えない部分についてシステムがチェックをします。例えばIPアドレスなどですね。メールアドレスにしても、そのドメインが日本のものなのか、他国のものなのか確認しています。
さらに、購入者の使用端末の情報もチェックします。例えば同一端末を使用しているにもかかわらず複数枚のクレジットカードを使用しているような事例をシステムで検出し、怪しい注文については事前にブロックし受注を防ぎます。その結果、ASUKAをご利用いただいているお店では、目視での確認が減るとともに、不正利用が減少したと喜んでいただいています。
編集部
もう一つの「チャージバック保証サービス」は、どんな内容なのでしょうか。
渡辺さん
こちらはアクルが推奨している不正対策・不正検知システムでの審査を通過したにもかかわらず、チャージバックが発生してしまった場合に、その費用を保証するサービスです。
編集部
なるほど。どちらもECを展開している事業者にとっては、頼もしいサービスですね。
フルフレックス&フルリモートに徹する先進的な勤務体系

編集部
アクルさんの勤務体系は、フルフレックスやフルリモートを導入していらっしゃいます。会社としてもワークライフバランスは推進していらっしゃるのでしょうか。
渡辺さん
はい。勤務体系はフルリモート勤務であり、コアタイムのないフルフレックスタイム制です。場所や時間に縛られず仕事ができますし、時短勤務や副業もOKです。
また、書籍購入制度や資格取得補助制度なども導入しており、クレド(※)では「家族、健康を優先せよ」と伝えています。働きやすい環境が整っていることは間違いないと思います。
(※)クレド:会社の全メンバーが実践すべき行動指針のこと。
編集部
フルリモートの運用にあたっては、いろいろなルールがあると思います。例えば出社日については、どんな設定がなされているのでしょうか。
渡辺さん
出社については基本的に会社のルールはなく、チームに任せています。例えばチームごとに月に1回のリアルミーティングを開催し、そのときは会社が費用を負担してメンバー全員でランチを食べるなど、チームとして一番合理的なルールを設定してもらっています。
ただし、2~3カ月に1回設定している役員との1on1は、すべてのメンバーが出社しています。これをあわせると、メンバーの出社日数は月に1~2回程度ですね。
コミュニケーション円滑化のための工夫
編集部
リモートワークをメインにしている中で、メンバー間のコミュニケーションをより円滑化するために、どんな工夫をされていますか。
渡辺さん
アクルはチーム内でのミーティングが多く、コミュニケーションを図りやすい環境だと思います。そのうえで円滑化するための工夫は、例えばペアで顧客対応する営業部隊ですね。二人一組なので、顧客情報などは常にリアルタイムで共有できています。
また、オンラインによる顧客とのミーティング終了後に、メンバー同士で必ず振り返りを行うようにしています。リアルで顧客対応を行う場合、顧客先への行き帰りの道中でメンバー同士が必ず情報をやり取りをしていました。「今度のお客様は、こういうことを強化している」とか「今日のミーティングは、ここがうまくいった」とか。
ところがオンラインのミーティングでは、会議が終わったらそこでメンバー同士の会話も終了してしまいます。それではもったいないということでアクルでは、お客様とのミーティングの終了後に、必ずメンバー同士で内容を振り返る時間を設けています。リアルの時と同じように確認したり、共有したりします。これをやるようになってからは、コミュニケーションが一段とスムーズになったという印象があります。
編集部
リアルのよい部分を、オンラインにも取り入れたのですね。他にもコミュニケーション円滑化のために工夫されていることがありますか。
渡辺さん
これは開発のエンジニアチームの話ですが、彼らは週に1回のミーティングの中で、仕事の話とプライベートの話とをミックスしたものを、常にテーマの一つとして取り上げています。こうすることで、たとえオンラインでしかコミュニケーションをしたことがないメンバーについても、その方の人となりがある程度はわかります。そういった仕組みを取り入れています。
水曜日の午後を一斉休暇とする、独自の働き方改革
編集部
アクルさんでは働き方改革を推進するために、2023年から独自の取り組みをスタートしたと伺いました。どのような制度なのでしょうか。
渡辺さん
2月からスタートした「水曜日午後の一斉休暇」です。これは基本的に「ブルーマンデーがない職場へ」をコンセプトとした取り組みで、最終的には「週休三日制の導入」を目指しています。
ただし、いきなりの週休三日制には無理があるので、まずはトライアルとして水曜日午後の休みをスタートしました。2月と3月は月に1回ずつ、そして4月には月に2回、水曜日の午後を休みとしました。
編集部
どういったお考えから、水曜日の午後を休みとする制度が始まったのですか。
渡辺さん
近年の社会情勢もあり、リモートワーク体制が浸透し始めたころから「働き方改革」という言葉が注目されてきました。これをアクルに置き換えたときに、働き方改革としては「何ができるのか」という問題意識が発端になりました。というのもアクルの場合、先ほどもご説明したように勤務体系や福利厚生、副業への対応などについては、すでに前向きに取り組んでいるという自負があったからです。
編集部
確かに、すでに「働き方改革は完了している」という印象です。
渡辺さん
そうなんです。ただし、これだけでは目新しさがなく、どこの会社でもやっています。そうではなく、アクルならではの働き方改革として「何ができるのか」を改めて考えてみました。
そこで、前々から自分自身で思っていたことなのですが、月曜日の朝は気分が重たいというのがあります。ベンチャーや大手などいろいろな環境の方にも聞いたのですが、月曜日の朝は多くの方が気分が重く、エンジンのかかりが悪い。まさにブルーマンデーが存在していました。これはフルリモート勤務でオフィスへの出社がない環境でも、やはり同様でした。
だったら、このブルーマンデーという世間にある概念の破壊に挑戦することが「アクルらしい働き方改革ではないか」と考えたのです。アクルで働いたらハッピーマンデーとまではいわないですが、少なくとも「月曜日がそれほど重たくはない」というレベルにまでは改革できないだろうか。月曜日から生き生きと働けるような、そういったことができないかと考えました。
では月曜日を休みにするのかというと、それでは火曜日が重たくなるだけの話で目指したい方向性ではなく、いろいろと思い巡らせてみたところ、月曜日がそれほど重たくならない週があることに気づきました。一週間の中に祝日のある週で、そういう週の月曜日はちょっと気分が軽い。
そこで「週の真ん中の水曜日を休みにするというのはどうだろうか」ということで、社会実験的に制度をスタートさせてみました。
休みにやることは、「重要度の高いテーマ」から自分で選択
編集部
ブルーマンデーの解決が働き方改革のゴールですか。まさしく御社ならではの働き方改革だと思います。
渡辺さん
ありがとうございます。最終的には週休三日制を目指しているのですが、今はまだ道半ばです。現在のトライアルの水曜午後休暇については、もちろんその分の給与は発生していますし、アクルとしては「メンバーの皆さんの時間に投資します」というスタンスです。
もっとも、単に休みが増えただけで無駄に過ごしては無意味だろうという考えもありました。そこで「時間の使い方を一度立ち止まって考えてみませんか」ということを全社員に問いかけてみました。何を問いかけたかというと、自分の中で常々「これをやりたい」とか「こういうことができたらプラスだ」と思いつつも、「取り組めていないことはないですか」ということです。
今すぐにやる必要はないけれど、やれば必ずプラスになる。例えば英語を話せるようになると、コミュニケーション力や情報収集力がアップし、ビジネスパーソンとしての幅が広がるといわれます。ところが、すぐに必要なわけではないから、結局は先延ばしになり2年経っても3年経っても何もできていない。誰にでも、そういうものってあるのではないでしょうか。
要は、時間管理のマトリックスで定義づけられている第二領域(※)です。ここに属している「緊急性は低いけれども重要度の高いテーマ」をご自身で考えて、これに使うための時間として、この休みを使ってくださいと提案をしました。
(※)第二領域:スティーブン・R・コヴィー著「7つの習慣」で紹介されている概念で、緊急度と重要度でタスクを分類したときの「緊急ではないが重要」という領域を指す。
編集部
目的を明確にすることで、休みを真に有効なものとするのですね。
渡辺さん
そうです。この休みの導入にあたっては事前に、「水曜日の午後は、どう使ってもいいのか」という質問が多く寄せられました。「仕事をしてもいいのか」とか、逆に「ダラダラしてもいいのか」など。
それについては、「ご自身が考える第二領域の問題です」とお答えしています。ご自身が「今はとにかく仕事をしたい」とか、あるいは「のんびりしたい」という明確な意思を持っているのであれば、「何をやっていただいてもけっこうです」と。アクルは副業もOKなので、もし働きたいのであれば、この休みを使っていただいても、まったく問題ありません。
改革により前向きな変化あり。ステークホルダーにも良い影響を広げたい
編集部
先ほど、アクルさんとしての重要なキーワードとおっしゃられていた「成長」にも、水曜日の午後休暇は役立ちそうですね。
渡辺さん
そう思います。この休暇の目的の一つは、メンバーの皆さんにとって、よい変化のきっかけにしていただきたいということです。「やりたいと思っていたけれど、やれていない」というテーマに対して、しっかりと時間をあててコツコツと取り組んでいく。そうすれば、去年の自分とは違う自分になれるはずです。
人としてさらに成長したり、さらなる魅力を備えられるのではないか。社員の皆さんには、もっとハッピーになっていただきたい。そして、外部の方から見て「アクルの社員は皆が幸せそうだ」となれば、お客様やステークホルダー全体にまで、良い影響が広がるのではないかと考えています。
さらにいうと、この休暇の導入で働く時間が少し短くなって労働時間が減りますから、その分、業務の効率化を考えなければいけない。このテーマにメンバー全員が取り組むことで、会社全体の生産性アップに繋がっていくだろうとも考えています。
編集部
実際に休みを経験したメンバーの皆さんからは、どんな声が聞こえてきましたか。
渡辺さん
2月の第1回目の休暇終了後にアンケートを実施しました。「休みを何に使いましたか」という設問では、リラックス(68.4%)、学び(42.1%)、健康・エクササイズ(31.6%)、趣味(15.8%)、家族(15.8%)という回答が上位に並びました。
そして、具体的な声としては「計画通りに3時間勉強、3時間美容に費やせたため100点です」や「家族のために時間が費やせたことで満足感が得られました」といった前向きなものや、「土日は家族のための時間で、平日に仕事のこと以外に自分のことを考えられる時間は非常にありがたい」という感想が目立ちました。
また、「なんとなく仕事のことが心配でしたが、完全に気持ちを切り替えてリフレッシュする方が有意義に過ごせる気がしました」や「まだ1回目なので感覚をつかめていない印象です」といった、今後の取り組み方を模索するような声もあがっていました。
編集部
お客様からの反応はいかがでしょうか。平日の休暇ということで、中には唐突な印象を持った方もいるのではないですか。
渡辺さん
おっしゃる通りですね。アクルはアプリケーションを24時間365日、SaaSとして提供しているサービス業でありながら、土日はしっかりと休んでいる。そして今度は「平日にも休みを取るのか」と。これはかなりチャレンジングです。
ですから、まずは会社として「アクルは〇月〇日の水曜日の午後は一斉休業します。この日にいただいたお問い合わせの回答は木曜日以降になります」という案内を、事前にお客様へ行いました。担当個人が休んでいるのではなく、会社として休んでいるということを、お客様には事前に告知をするようにしました。
それをしないと、例えば水曜日に届いたメールに即答しなかったということで、担当者がお客様からお𠮟りを受ける可能性もあります。そうなったら、水曜日の休暇が継続できません。会社としての休みであることを、これまで以上に明確に打ち出していき、「アクルの水曜午後は休業」ということをご理解いただきたいと考えています。
ミッションは「『決済』にかかわるあらゆる課題を解決」すること
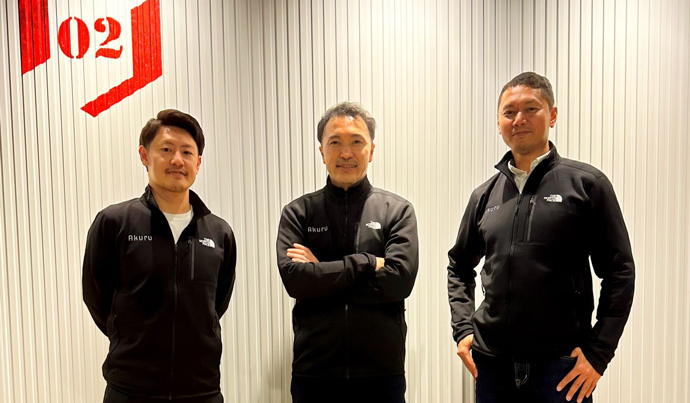
編集部
アクルさんはミッションとして「『決済』にかかわるあらゆる課題を解決していく」を掲げています。この明確な方針のもと、メンバーの皆さんはどんな思いで日々、仕事をされているのでしょうか。
渡辺さん
基本的には、クレジット決済に関する不正の根絶が、メンバー共通の思いであり、目的であることは間違いありません。
最近では転売ヤーの動きにも注目しています。先日もテレビで、人気のキャラクターカードの不正転売に対して子どもたちが「転売ヤー、いい加減にしろ!」と叫んでいるのを見て、「オー」っと思いました。これについてもアクルのノウハウで、不正を減らすことは可能だと思っています。
アクルには決済畑の出身者が多いですし、決済という身近な分野において、自分たちのニッチで専門的なノウハウを生かすことができます。子どもたちの夢や楽しみを守るためにも、ぜひ解決したいテーマだと思っています。
編集部
皆さん、正義感に燃えていらっしゃるのでしょうね。
渡辺さん
確かにそうです。先ほども「不正利用者と戦っている」といいましたが、日々データをチェックしていると「不正利用者がたくさん現れたぞ」とか「これは何とかして止めなければ」というシーンに遭遇することが多いです。
そういったときには社内の連携を一段と強め、時にはお客様も巻き込みながら、一緒になって悪に立ち向かっていく。メンバー全員が、そんな思いで仕事をしていることは確かです。
編集部
そのためにメンバーの皆さんは日々、スキルや知識をアップグレードされているのでしょうね。
渡辺さん
その通りです。メンバーには常に「いつもと同じルーティンワークはないよ」といっています。不正利用者も手をかえ品をかえ、いろいろと挑んできますし、テクノロジーもどんどん変わっています。明確な正解がない中で、最適なものを探し求めていく。この気構えを忘れずに、「いろいろなことにチャレンジしよう」と話しています。
そういうプロセスを通じて、自らを成長させるきっかけをつかんでいただきたいと考えています。アクルにとって「成長」は非常に重要なキーワードです。昨日できなかったことが今日はできる。去年できなかったことが今年はできる。そういう成長がとても大切だと考えています。
アクルのイメージは「大人ベンチャー」な会社
編集部
渡辺さんは、現在の「アクル」をどんなイメージの会社だと感じていらっしゃいますか。
渡辺さん
お客様などからよくいわれるのは「大人ベンチャーな会社」ということですね。確かにそういわれると、ベンチャーではありますが平均年齢は比較的高めです。
しかも、メンバーの雰囲気も若くてキャピキャピという感じではなく、比較的落ち着いた印象の方が多いです。20代の営業メンバーも何人かいるのですが、20代に見えないぐらい落ち着いています。ですから「大人ベンチャー」という表現は、けっこう的を射ていると思います。
あとは事業が決済関連なので、比較的堅い業界ではあります。ただし、その堅い業界の中において、「スピード」を意識しながら取り組んでいる会社だと思います。
採用のキーワードは「正義感」「真面目」「誠実」

編集部
では最後に、採用について伺います。アクルさんが採用するにあたって、「こういう方が望ましい」と考えるのは、どんなタイプの方でしょうか。
渡辺さん
最近は「決済について経験があります」という方が増えてきました。ところが決済に「セキュリティ」というキーワードが加わると、その数は一気に減ります。
そのため、まずは「決済とセキュリティがわかっている。そういうスペシャルな人材になりたい」と思う方に、ぜひ来ていただきたいです。そして、いろいろなお金の支払い手段について、研究したり学んでみたいという方も大歓迎です。
アクルでは決済に関するいろいろな情報が飛び交っています。そして、いろいろな決済業務を学ぶことになりますので、キャリアという意味合いでも、決済に関するスキルやノウハウが自然と身につくことは確かです。
あとは基本的に、正義感の強い方がマッチすると思います。弁が立つとか、話がうまい必要はありません。物静かで口下手であっても、真面目で誠実であれば何の問題もない。面接でもやはり、真面目、誠実な雰囲気を持っている方が通りやすいと思います。そういう方に、ぜひチャレンジしていただきたいです。
編集部
採用のポイントは「正義感」、そして「真面目」「誠実」ですね。これらのキーワードは、確かにアクルさんの社風を表していると思います。本日はありがとうございました。
■取材協力
株式会社アクル https://akuru-inc.com/
採用ページ https://www.wantedly.com/companies/akuru-inc


