派遣社員でも社会保険に加入できる?

社会保険に加入できるのは正社員だけ?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際は派遣社員でも一定の条件を満たしている場合は、むしろ加入が義務付けられているのです。
社会保険とは?
社会保険とは、一般的には健康保険と厚生年金保険の2つを指します。広義では他に、介護保険・雇用保険・労働者災害補償保険の3つを含みます。
- 健康保険
加入者と、その扶養者の業務外の傷病・出産・死亡等に対して給付される保険です。例えば、病気やケガをした際に病院の医療費の7割給付が受けられ、出産の際は出産育児一時金42万円と出産手当金が支給されます。(75歳以上は後期高齢者医療制度に加入する為、健康保険には加入できない)
- 厚生年金保険
加入者の老齢・障害・死亡に対して給付される保険です。加入中に障害を負った場合や加入者死亡の場合は遺族に支給されます。(満70歳以上は加入できない)
社会保険に加入するための条件
社会保険に加入するための一定の条件は以下です。
- 雇用期間
2ヶ月以上の雇用契約(期間中契約に1日の切れ間がない)であれば契約期間の初日から加入することができます。
- 労働日数・労働時間
派遣元である派遣会社の1ヶ月の所定労働日数の3/4(15日)以上、1週間の所定労働時間の3/4(30時間)以上が加入の条件です。
(短期労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、1年以上の雇用見込み、厚生年金被保険者数等の条件を全て満たす場合に加入する※学生は除外 )
社会保険に加入するメリット・デメリット
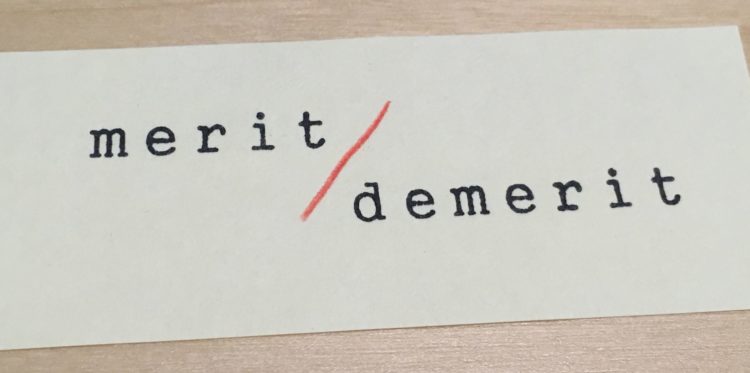
社会保険料は派遣先の企業ではなく、派遣会社と派遣スタッフが負担します。健康保険と国民健康保険の違いや、社会保険の意義を通して社会保険のメリット、デメリットをみていきましょう。
メリット
アルバイトの方が派遣社員に転職して良かったと感じるメリットのひとつが社会保険の加入です。アルバイトの場合ほとんどの方が国民健康保険料を全額自己負担で納めています。
派遣社員の場合は派遣会社が社会保険の手続きをしてくれる上に保険料を一部負担してくれるので自己負担は軽減されます。毎月社会保険料を計算して給料から差し引きし、派遣会社がまとめて払ってくれるので安心です。
例えば病院で診察を受ける場合、健康保険・国民健康保険ともに医療費の自己負担は3割で同率です。しかし病気や怪我で仕事を休む場合に、健康保険では賃金の6割が支給される傷病手当金制度があるのに対し、国民健康保険は支給されません。
出産時の出産育児一時金は双方支給されますが、健康保険の場合は出産手当金も給付されます。
また健康保険は世帯ごとに保険料を算出するので、被保険者が扶養する親族には保険料がかかりません。国民健康保険は個人単位で保険料がかかり、自治体や年収によって算出方法などが違います。
このように国民健康保険より、派遣会社で加入する健康保険のメリットはたくさんあります。
デメリット
条件を満たす場合社会保険の加入は義務ですから、強制的に加入させられているというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。 お給料から保険料が差し引かれ、単純に手取り金額が減ります。
1ヶ月のお給料から、人によっては2~5万円引かれていると確かに損した気分になりますね。しかし、本当にデメリットなのでしょうか。
上記の社会保険に加入するメリットを考えてみれば、手取りが減ったように感じるのは一時的なものだとわかるでしょう。
その分と言ってはなんですが、交通費のかからない近場を希望条件にあげたり、自転車などの通勤手段が使える会社、社員食堂のある会社など、自分の条件に合った派遣の仕事を選ぶなどして他の費用を抑えてはいかがでしょうか。
条件を指定して仕事を選べるという派遣社員のメリットを活かしましょう。
健康に自信があるから健康保険は必要ない、年金をもらえる年齢にはどうなっているかわからないから厚生年金は必要ないという方もいらっしゃいます。現時点では健康ですが、いつ何時病気や怪我に見舞われたり、何らかの事情で働けなくなるかもしれません。
先のことは誰にもわからないものです。備えあれば憂い無し!自分を支えることが社会を支えることにつながっているのです。
また派遣社員の場合、就業時間や日数が増えてフルタイム勤務に変更したときなどは注意が必要です。社会保険の加入について派遣会社の担当に確認しましょう。
派遣会社ごとの社会保険制度

社会保険制度は、派遣会社が一般的に利用する人材派遣健康保険組合と、派遣会社がそれぞれに設けている組合健保があります。
- 人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」・全国健康保険協会管掌健康保険「協会けんぽ」
先ほどの社会保険加入条件と同じ条件で加入することができます。(2ヶ月以下の短期雇用でも契約が継続された場合、2ヶ月目以降の仕事初日から加入)
また、2ヶ月以上加入していれば仕事がない待機期間中も任意継続が可能です。
- 組合管掌健康保険(組合健保)
加入条件は一般の社会保険と同じような場合が多いです。ただし、待機期間の任意継続特典はないので注意が必要です。
社会保険料は収入によって決定されます。毎月の給料には差が生じるため、標準報酬月額(※)を基準に算出します。
以下では各派遣会社の加入保険の種類や福利厚生についてご紹介します。(※毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率)
スタッフサービス
派遣といえば、、というくらい有名なスタッフサービス。
求人件数が多く、幅広い職種に対応しているので仕事の決まるスピードが速いことが人気のポイントです。
協会けんぽ
テクノ・サービス(スタッフサービスのグループ会社。主に製造業等の派遣)で就業の場合は「協会けんぽ」に加入します。
一般保険料率
都道府県別に設定されており、被保険者と事業主が折半で負担。以下例
- 一般保険料率 (東京)
被保険者 6.38%
事業主 3.43%
合計 9.81%
- 一般保険料率(大阪)
被保険者 6.79%
事業主 3.43%
合計 10.22%
福利厚生
- 健康診断・・・無料の一般・付加健診、協会けんぽが一部負担する乳がん・子宮頸がん検診・生活習慣病等の特定健診等
- 家庭用常備薬のあっせん・・・健康維持のための常備薬等を特別価格販売
- ホテル等の優待・・・契約ホテルや宿泊施設の優待価格利用
- スポーツ施設等の優待・・・スポーツジム等の契約施設のお得な法人価格利用
協会けんぽ公式HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
リクルートスタッフィング
リクルートグループはCMでもお馴染ですね。
大手企業の求人も多く、安心のサポート体制が充実していることで定評があります。
リクルート健康保険組合「けんぽっぽ」に加入します。
一般保険料率
被保険者 3.85%
事業主 4.15%
合計 8.0%
福利厚生
- 健康診断・・・人間ドック・ファミリー健診・歯科検診・メタボリックシンドローム特定健診等
- フィットネスクラブの優待・・・契約施設の法人会員料金利用
- メンタルヘルスサポート・・・健康相談、介護・育児相談
- 一部負担還元金・・・リクルート健康保険組合独自の給付。1ヶ月の病院窓口支払い分の医療費から自己負担の上限額(※)を引いた残額が払い戻されます。
※付加給付の自己負担上限額は標準報酬月額によって異なります
けんぽっぽnet公式HP:http://kempo.recruit.co.jp/
アデコ
求人数が多く、アデコグループは人材派遣企業でも最大規模です。
語学講座などのサポートもあり、外資系企業に強いことでも有名です。
アデコでは人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」に加入します。
はけんけんぽの公式HP:http://www.haken-kenpo.com/
テンプスタッフ
人材派遣業界トップクラスの業績を誇るテンプホールディングス。
スキルアップやワーキングマザー支援など福利厚生が充実していることでも知られています。
テンプスタッフでは人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」に加入します。
はけんけんぽの公式HP:http://www.haken-kenpo.com/
ハタラクティブ
東京・神奈川・千葉・埼玉エリアに特化した、紹介予定派遣に強い派遣会社です。
条件を満たす場合、ハタラクティブを運営するレバレジーズ株式会社の社会保険に加入することになりますが、 紹介予定派遣期間を過ぎれば正社員として派遣先の会社の社会保険に加入します。
このように派遣会社ごとに社会保険制度は違います。
複数の派遣会社に登録し、それぞれの派遣会社のエリア別・職種別・就業形態別の強みや、保険制度・福利厚生の特徴を比較してみましょう。
複数社の派遣会社の求人件数総数は、1社だけに登録しているのとは比べものにならないほど多いです。より早く、より好条件で希望の仕事に就くことができるでしょう。
