働き方や人材活用、社員教育、そして社風などで独自の先進性を打ち出し、成長を続けている企業を取材させていただく本企画。今回はIT技術教育とビジネススキル教育を中心とした人材育成事業を展開するトレノケート株式会社にお話を伺いました。
トレノケート株式会社とは
1995年12月に設立されたトレノケート株式会社は、人材育成を通じて社会貢献することを目指しています。そのための指針としてビジョン(「世界を変える『人』を育てる」)、ミッション(「人材育成の未来を主導する」)、バリュー(「チャレンジを楽しむ」)を掲げており、この三つをメンバーが共有。チャレンジを奨励する社風のもと、意欲的に事業を展開しています。
| 会社名 | トレノケート株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階 |
| 事業内容 | IT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成 |
| 設立 | 1995年12月6日 |
| 公式ページ | https://www.trainocate.co.jp/ |
トレノケート株式会社の大きな特徴の一つは、テレワークに積極的に取り組んでいることです。テレワークを一度でもしたことのある従業員は9割を超えています。
その環境でもコミュニケーションが不足しないための対策をうかがうとともに、テレワークを円滑化する工夫やチャレンジを奨励する社風、学び合う企業文化などについてお話を聞きました。さらには、採用における重要なポイントもあわせてうかがいました。
IT技術とビジネススキルを両輪とした人材育成事業

▲世界のトップベンダーから贈られたアワードの数々
編集部
まずは事業内容についてお聞かせください。
林さん
弊社はIT技術教育とビジネススキル教育を中心とした人材育成事業を展開しています。親会社のトレノケートホールディングスは現在、世界15の国と地域でこの事業を推進しており、当社は日本国内の事業を担当するグループ会社です。
一番の特徴はIT技術だけでなく、ビジネススキルやヒューマンスキルなどの講座も豊富に提供しているため、両者を組み合わせた総合的な育成メニューを提案できることが大きな強みです。
提供している講座は1,500以上あり、新入社員から経営層までの全階層をカバーしているので、お客様のさまざまなニーズにお応えできます。
弊社のこうした教育体制は、AWS様やCisco様、Microsoft様といった世界有数のITベンダーからも高く評価されています。優れたラーニングパートナーとして毎年さまざまなアワードを受賞しており、その数は通算で70回以上になります。
2022年11月には、「Top IT & Technical Training Companies」に3年連続で選ばれました。これは世界最大級の人材育成情報プラットフォームTraining Industryが、世界で最も優れた20のITトレーニング企業を選出するもので、日本からの受賞は弊社だけでした。
どこにも属さない中立的な立場だからできる顧客提案

▲中立的な立場で常に顧客本位の講義を提供
編集部
まさしく世界トップレベルのITトレーニング企業なのですね。それだけ講師陣や研修メニューのレベルが高いのだと思います。
林さん</p >
ありがとうございます。レベルの高さに加えて、弊社が中立的な立場の研修企業であることも、評価をいただけている要因の一つだと思います。特定の製品やサービスに縛られないニュートラルな企業ですから、お客様に提供するツールやサービスなどにも一切の縛りがありません。お客様にとって本当に必要なものを、真剣に考えて提供しています。
編集部
「このソフトを使わなければいけない」といった制限がないので、本当の顧客志向でサービスを提供できるわけですね。
林さん
そうです。研修形態にしても、集合形式でもオンライン形式でもご要望に合わせられます。さらには「一社向け研修」への対応も万全です。課題や目指すべき方向などのヒアリングをして、そのお客様にフィットする研修メニューをご提案しています。また複数の研修メニューをご希望のお客様にも、一括でお任せいただいています。
ニーズの高いDX講座で独自の研修メニューを提案
編集部
1,500以上ある研修メニューの中でも、最近特にニーズが高いと感じるものは何でしょうか。
林さん
先日、展示会に出展したのですが、そこで感じたのはDXですね。「DXが注目されているから何かをやらなければいけない」や「DXの部署に異動になったけれど、何から手をつければいいのかわからない」という声をずいぶんとお聞きしました。キーワードとしてのDXは知っているけれど、「何をすればいいのかわからない」というお客様が、まだとても多いように感じます。
編集部
「DX」の意味がよく知られていないまま、言葉だけが世の中に先行して広まっているのでしょうね。
林さん
そう思います。ですから、「何をすればいいのかわからない」というお客様が、「DXとは何かを他者に説明できる」「ポイントをおさえてDXを推進できる」「DXに必要なテクノロジーの概要を知っている」「自分なりのDXの始め方を整理できている」状態を目指す「DXファーストステップ」といった研修も開発しました。
編集部
その時代にあった研修開発も進めているのですね。
林さん
そうです。いろいろな会社がDX研修をカリキュラム化していますが、弊社の場合は、マインド部分などIT技術以外の部分も研修メニュー化できます。DXについても、「なぜ、取り組まなければいけないのか?」といった必要性から学ぶことを提案しています。そうすることで、これ以降の技術的な研修が、とてもスムーズに進められるからです。
人材育成を通じて社会貢献するための3つの指針

▲学びやすさを最優先した集合研修用の教室
編集部
人材育成事業を展開する中で、メンバーのみなさんが念頭に置いている指針を教えてください。
石川さん
弊社は人材育成を通じて、社会に貢献することを目指しています。そのための指針として「トレノケートのビジョン、ミッション、バリュー」の3つを掲げています。まずビジョンですが、これは「世界を変える『人』を育てる」です。世界をよりよく変えられる人材の育成を通して、社会に貢献することを目指しています。
ミッションは「人材育成の未来を主導する」です。人材育成の未来を主導して、向上心を持ったすべての方を支援します。そしてバリューには「チャレンジを楽しむ」を掲げています。常に挑戦し続け、それを楽しむことを、弊社はとても重視し奨励しています。
教えることが大好きなプロフェッショナルな講師陣
編集部
ビジョン、ミッション、バリューの3つを共有しているメンバーのみなさんには、マインドや雰囲気、資質などで共通するものがありますか。
石川さん
会社全体としての雰囲気は、プロの集団という感じです。弊社には4つの本部があります。営業本部、マーケティング本部、管理本部、そして講師が所属するLS(ラーニングサービス)本部です。この中でLS本部が象徴的な存在だと思います。
所属する講師は技術担当とビジネス担当とにわかれるのですが、共通するのはみなさんがそれぞれの分野のプロフェッショナルで、教えることが大好きだということです。講師としての仕事に情熱と誇りをもっています。また、弊社の講師達は30~50代の方が活躍しており、落ち着いた雰囲気です。
営業の場合は、20~50代まで幅広い方が在籍していますが、所属チームなどで多少の違いがありますが、例えば大手企業の担当者からは、「戦略的にお客様を獲得するプロセスが、とても刺激的で楽しい」という声を聞きます。大手企業様の場合、決裁権者がどなたかわからないケースが大半ですので、こうした企業様との取引を実現し、いかに大きく発展させるか。そういうチャレンジを楽しんでいるようなイメージですね。チームのメンバー同士でサポートし合いながら、取り組んでいます。
編集部
林さんが所属しているマーケティング本部はいかがでしょう。何か共通する資質がありますか。
林さん
私は入社してまだ1年未満ですが、この間で強く感じたことは、教える体制ができているといいますか、相手の成長のために行動する方が多いということです。同僚と普通に会話をしていても、「この表現は、もっとこうした方がいいのでは」といったアドバイスをもらうことが多いのです。上長や先輩との会話でしたら、なおさらですね。
編集部
お互いに教えあって成長するということが、文化として定着しているのでしょうね。
林さん
はい。それを強く感じます。
自社の研修メニューを受講できる学びのシステム
編集部
教えあうことが文化ということですと、やはりメンバーのみなさんの向上心は旺盛なのでしょうね。
石川さん
はい。講師は日進月歩のIT業界にあって、知識のブラッシュアップが必須です。しかしこれは他のメンバーも同様で、学ぶことに意欲的な方が多いと思います。
林さん
弊社では、社内の研修メニューを社員が受講できるのです。入社して真っ先に、とても魅力的な制度だと思いました。学びたいという意欲があって、研修に参加する時間をきちんと作りさえすれば、いくらでも成長出来ると感じています。
編集部
それは素晴らしいですね。その制度は講師の方からみても、身内が受講者になることで講義の良否を確認する機会になりそうですね。
林さん
はい。講義が終わってから講師に、「どうだった?」と聞かれることがよくありますよ。
代表も含めフラットな文化が定着している
編集部
社内の上下関係はいかがでしょうか。例えば経営層とメンバーとのコミュニケーションには何か特徴がありますか。
石川さん
とてもフラットで風通しがよいと思います。役員やマネージャーとも、”さん”付けで呼び合っていますし、特に経営陣が自ら気さくに声を掛けてくださるなど、誰とでも話しやすい雰囲気です。
編集部
年齢や年次、役職などを問わない発言しやすい組織風土なのですね。
石川さん
そう思います。特に2022年4月に代表取締役社長に就任した早津(昌夫氏)は、もともとは大阪オフィスの営業メンバーとして入社しています。そこからキャリアを積み重ねてトップに就任していますので、私たちとの距離が本当に近いと感じます。弊社のフラットさは、こういったところにもはっきりと表れていると思います。
全部署・全従業員を対象とした独自のテレワーク体制

編集部
続いて働き方についてお聞きします。御社のテレワークへの取り組み状況をお教えください。
石川さん
弊社はテレワークを積極的に推進しており、2022年11月には、総務省から「テレワーク先駆者百選」に選出されました。これはテレワークの普及促進を目的にしたもので、弊社は十分な実績を持つ企業として公表されました。
編集部
それはすごいですね。御社のテレワークには、どんな特徴がありますか。
石川さん
一つは全部署・全従業員がテレワークの対象であること。アルバイトも対象です。そしてもう一つが、出社日数などを部門やチーム内で自由に調整できることです。日数などについては、会社としての上限を設けたり、出社日数の指定はありませんが、何かあれば出社できる準備だけはしておく必要があります。
編集部
出社日数に規定がないというのは、確かに先進的ですね。ちなみに林さんは、出社と在宅の比率がどのぐらいなのですか。
林さん
私はほぼ在宅で勤務しています。往復の通勤時間をかけるなら、テレワークの方が効率的だということで、出社は月に1~2回です。
編集部
全社的にみて、出社とテレワークはどのような比率なのでしょうか。
石川さん
例えば営業の場合、9割ぐらいがテレワークです。ただし、担当するお客様によっても異なりますので、必要があれば出社することもあります。また、出社とテレワークが半々ぐらいという部署やチームもあります。全社的にもテレワークがかなり浸透していますので、オフィスへの出社は1~2割程度です。育児や介護など、家族のケアと両立しながら働きやすい環境だと思います。
編集部
勤務時間はいかがでしょうか。
石川さん
弊社はフレックスタイム制度がありますので、社員はご自身の働き方に合わせて自由に選択することが出来ます。フレックスタイム制度にはコアタイムが設けられており、時間は10時~16時です。また、テレワーク手当という補助が会社から支給されます。
Teamsのフル活用でチーム内のコミュニケーションを活発化
編集部
それだけテレワークが進んでいる環境ですと、実際に顔を合わせて話す機会が少ないと思います。社内のコミュニケーションについては、どんな工夫をされていますか。
石川さん
基本的にはMicrosoft Teamsのチャットや電話などを利用しています。私がマネジメントしている人事チームの場合は、Teamsのグループチャットを使って積極的にやり取りをしています。
もともと、人事チームは出社と在宅とが半々でしたが、今年、テレワークの定着を受けて新宿オフィスを縮小したこともあり、テレワーク中心にシフトしました。
一方で、私たちの仕事は、チームで進めることも多く、チーム内のコミュニケ―ションは非常に大切だと考えていますので、そこでグループチャットを積極的に使うことにしています。ここでは、仕事始めの挨拶からスタートして、ランチタイムの休憩やちょっとした雑談なども、こちらのチャットを通じて会話しています。みんなでワイワイとおしゃべりする感じで投稿していますので、対面でのやり取りとは違いますけれど、コミュニケーション不足はまったく感じません。
編集部
なるほど。林さんはいかがですか。
林さん
そうですね。チャットでうまく伝わらないときには、Teamsの通話機能を使い、一対一で直接会話しています。上長や先輩からは「気軽に電話をしてね」と声をかけてもらっています。
編集部
テキストコミュニケーションだけでなく、直接の対話においても気軽に連絡がとり合える雰囲気になっているのですね。
林さん
はい。まったく気にせずに連絡しています。
社内の意思疎通を円滑化するサンクスポイント制度
編集部
コミュニケーションの円滑化で、他に取り組んでいることはありますか。
石川さん
2022年4月から始まった「サンクスポイント制度」も、テレワークでコミュニケーションを活性化させる工夫の一環です。先ほどお話ししたMicrosoft Teamsは、主にチーム内のコミュニケーションを意識していますが、サンクスポイント制度の狙いは他部署との連携の活性化です。社員同士で感謝を伝えあう機会を増やそうということでスタートしました。
編集部
どういった制度なのですか?
石川さん
毎月付与されるポイントを、100ポイントずつ、感謝したい相手にメッセージとともに送ります。感謝といっても、ちょっとした気軽なことでいいのです。日常業務のちょっとした感謝を形にして、部署を超えたコミュニケーションを増やしています。
編集部
感謝を書いた付箋を、机に貼り付けておくようなイメージですね。
石川さん
そんなイメージですね。例えば新しく入社した方に「入社おめでとう」のポイントをみんなで送るとか、そういったことにも活用しています。
テレワークの積極推進で変わりつつある採用方針
編集部
これだけテレワークに積極的ですと、採用方針も大きく変わってきているのではないですか。
石川さん
はい。例えば、昨年秋に入社された講師の方は岡山県にお住まいです。基本的には岡山県のご自宅からリモートでお仕事をして、必要な時だけ東京や大阪に出張します。こういう働き方はコロナ禍前には考えられなかったですね。採用の切り口が、ずいぶんと変わってきたと感じました。
編集部
今後は遠距離にお住まいの方なども、採用の候補者として普通に選ばれるようになりますか。
石川さん
ポジションによるかもしれませんけれど、可能性は十分にあります。
編集部
どのような経歴の方が入社されるのですか?
石川さん
講師になる方は、比較的IT業界からが多いです。現場経験があることも大切なためエンジニアやマネジメント、コンサルタント、など多岐にわたります。
講師以外のメンバーは、IT業界以外の出身者がとても多いです。最近では生命保険などの金融業界や人材業界の出身者など、人材育成というキーワードに興味を抱き、応募されるのだと思います。
採用の重点ポイントは「チャレンジを楽しむ」ことができるか
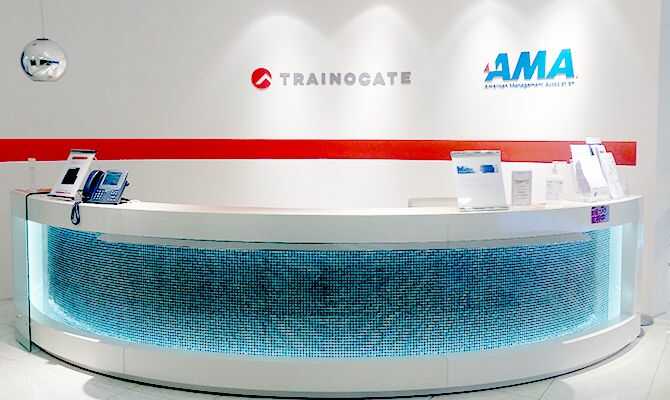
編集部
採用に当たって、重視しているポイントを教えてください。
石川さん
必要とする技術やスキルなどは基本的に現場の責任者が判断しています。人事として重視しているポイントは、「チャレンジを楽しむ」ことができるかどうかですね。
弊社は、これからより成長していくフェーズに入ります。今いるメンバーと一緒になってチャレンジを楽しむことができるかどうかが、ますます重要になってきます。この部分でスムーズに対応できる方であれば、メンバーとして自然に溶け込むことができると思います。
林さん
また、こちらは私自身の話ではないのですが、とある社員の採用面接のエピソードで深く印象に残った出来事がありましたので、そちらを紹介させていただきます。弊社の採用面接時、彼は介護と仕事の両立を考えていたので、トレノケートへの転職は最初、ハードルが高いだろうと覚悟していたそうです。
ですが、弊社は、彼の不安を取り除くために、介護をしながら働いている先輩社員を面接に同席させました。彼はその先輩社員の方と直接お話ができ、とても心強く思い、応募者のことをそこまで考えてくださるのかと、深く感銘を受けたそうです。そして、このことが、「この会社に入社しよう」と決断した一番の理由になったと聞いています。
やりたいことが明確な人には最適の環境
編集部
では最後に、御社に関心を持った読者へのメッセージをお願いします。
石川さん
やってみたいことを明確に持っていて、それを当社の業務とリンクさせられる方にとっては、とてもいいキャリア形成ができると思います。
一例を挙げると、数年前に語学を得意とする方が入社され、ベンダーを発掘する部署に配属されたんです。この方は在職中、さらに語学のスキルを伸ばして、結局、超大手のベンダーに転職されました。会社としては非常に残念な話ではありますが、トレノケートに入社してキャリアを積んで、次のステップに進むことができたのですから、それはとても素晴らしいことだと思います。弊社はすごく成長できる環境だと思います。
経営陣も「やりたいのならぜひやりなさい」と後押ししてくれますので、それがやりがいや達成感につながるのだと思います。ですから、やってみたいことが明確な方には、ぜひとも弊社でチャレンジしていただきたいです。
林さん
今のお話と似ていますが、私も面接で「入社したら何がしたいのか」ということを、何回も聞かれました。そして入社後も「何がしたいか」を繰り返し聞かれています。「やりたいことをやらせたい」という会社の思いが、とても強く伝わってきます。ですから「これをやりたい」ということを積極的に発信する方にとっては、弊社はとてもいい環境だと思います。
編集部
本日はありがとうございました。
■取材協力
トレノケート株式会社 https://www.trainocate.co.jp/
https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx
採用ページ https://www.trainocate.co.jp/recruit/index.html



